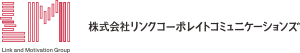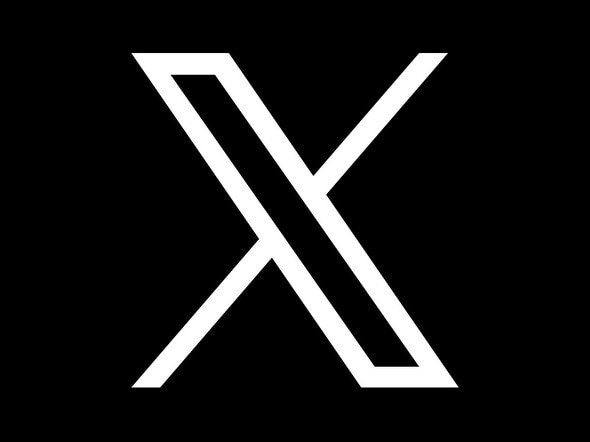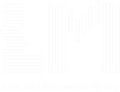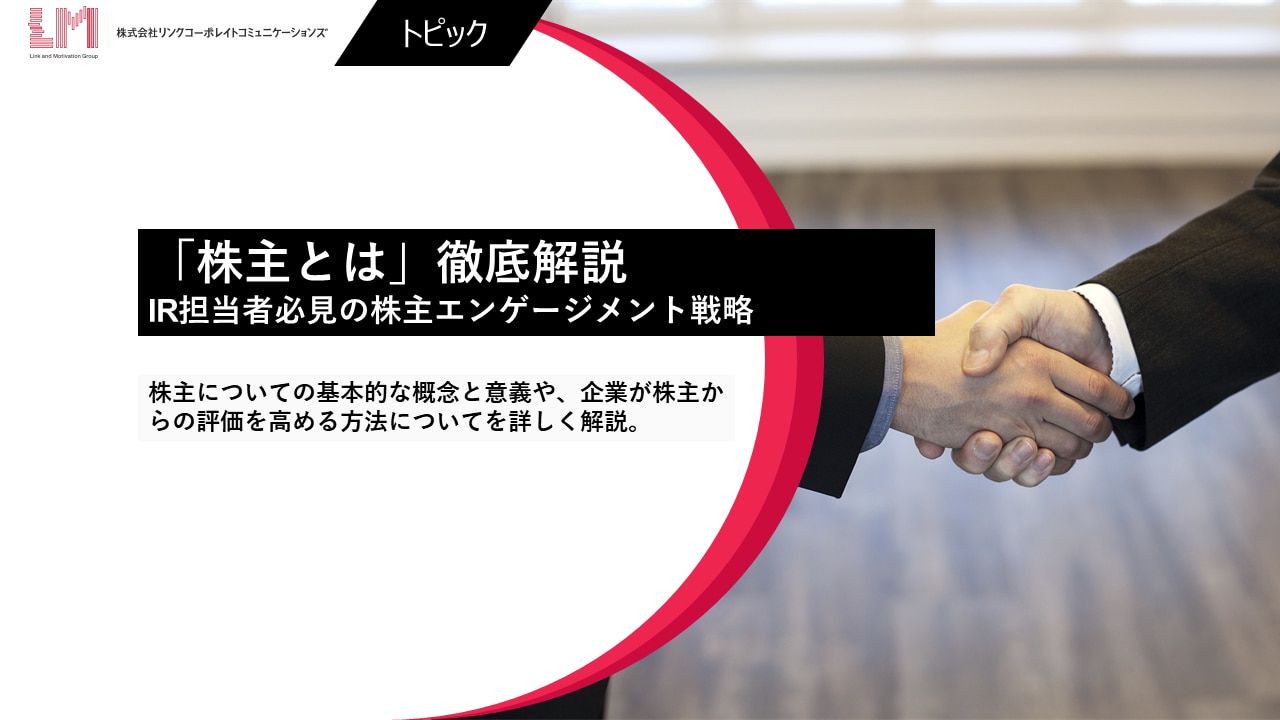
「株主とは」徹底解説:IR担当者必見の株主エンゲージメント戦略
株式投資に興味を持つ多くの人々が最初に知るべきキーワードの一つが「株主」です。株主とは、具体的にはどのような存在なのでしょうか?そして、株主になることで得られる権利や、株式市場での役割はどのように形成されるのでしょうか。この記事では、株主についての基本的な概念と意義を詳しく解説していきます。
目次[非表示]
株主とは?
株主とは、会社の株式を保有する者を指し、その結果として会社に対して特定の権利や義務を持つ者のことを言います。株主の概念は、近代の株式会社制度の発展とともに成立しましたが、その起源は古く、中世ヨーロッパの商人たちが共同で事業を行うための手段として「共同出資」の形を取っていたことに遡ります。
17世紀のオランダで、世界初の株式市場が成立した際、アムステルダム証券取引所が設立され、ここでの株式取引が活発化しました。これに伴い、株式を保有する者、すなわち「株主」の役割や権利が明確になり始めました。株主は、投資した資本に見合った配当を受け取る権利や、会社の経営方針に関与する権利を持つようになりました。
近代に入り、産業革命を背景に企業の規模が拡大すると、資本の集積が必要となり、多くの人々が小額の資金を出し合って大きな事業を支える株式会社が普及しました。これにより、株主という存在が一般的になり、その権利や義務が法制度として整備されていったのです。
現代では、株主は会社の成長や利益を共有するだけでなく、企業の社会的責任や持続可能性にも関心を持ち、その方針や活動に対して意見や要望を伝える役割も果たしています。
大株主とは
大株主とは、会社の発行する株式の一定の割合以上を保有する株主を指します。日本国内において「何%以上を保有していると大株主」という基準はありませんが、議決権のある発行済み株式の100分の10以上を保有する株主を「主要株主」といいます。また、発行済み株式総数の5%を超えて株式を保有した株主は、5%を超えて保有した日から5営業日以内に、内閣総理大臣に「大量保有報告書」を提出しなければなりません。
大株主の特徴としては、その保有する株式の割合が高いため、株主総会での議決権が強く、会社の経営方針や重要な決定に大きな影響を持つことが挙げられます。また、大株主はその経済的利益を最大化するために、経営者や取締役とのコミュニケーションを頻繁に取ることが一般的です。このため、経営の透明性や健全性を求める動きが強まることもあります。
機関投資家とは
機関投資家とは、銀行、保険会社、投資信託、年金基金などの金融機関や資産運用会社が株式を保有する場合を指します。彼らは大量の資金を運用するため、一般的には大量の株式を保有することが多いです。
機関投資家の特徴としては、専門的な知識や分析能力を持つことから、その投資判断は合理的であり、長期的な視点での投資が中心となります。また、企業の経営に対しても、持続可能性や環境、社会、ガバナンス(ESG)を重視する傾向があります。このため、機関投資家の動向や意向は、株式市場や企業経営に大きな影響を与えることが一般的です。
個人投資家とは
個人投資家とは、一般の個人が自らの資産を元に株式を保有する場合を指します。彼らはプロフェッショナルな投資家とは異なり、多様な背景や投資目的を持つことが特徴です。
個人投資家の中には、短期的な利益を追求するデイトレーダーや、長期的な資産増加を目指すバリュー投資家など、様々な投資スタイルを持つ者がいます。また、情報収集の手段や判断基準も多岐にわたるため、その動向は予測しにくいとも言えます。しかし、彼らは株式市場の活性化や流動性の提供に一役買っており、市場の健全な機能を支える重要な存在となっています。
▼個人投資家向け説明会についての詳しい解説はこちら
株主と株式市場の関係は?
株式市場は、企業が発行する株式の売買が行われる場所です。この市場において、投資家は株主となることを希望する株式を購入したり、既に所有している株式を売却したりします。株式の売買は、証券取引所において公開されている価格で行われ、この価格は供給と需要のバランスによって決まります。
株価の変動は、多くの要因によって影響を受けます。企業の業績や将来の成長見込み、経済全体の状況、政治的な出来事、金利の動き、外国為替の変動など、様々な要因が株価に影響を与える要素として挙げられます。また、投資家の心理や感情、市場参加者の予想と実際の数字とのギャップなど、非合理的な要因も株価の変動に影響を及ぼすことがあります。
株主としての投資戦略は、個々の投資目的やリスク許容度、投資期間などによって異なります。一般的に、長期的な視点での投資を推奨する意見が多いですが、短期的な取引を好む投資家もいます。重要なのは、自身の投資目的やリスク許容度を明確にし、適切な情報収集と分析を行いながら、冷静な判断で投資活動を行うことです。
株主と会社の関係
株主と会社の関係性は、資本主義経済の中核をなすものです。株主は、自らの資金を会社に提供することで、その会社の一部の所有者となります。この所有権は、保有する株式の数や種類に応じて異なる権利や義務を伴います。一方、会社は、株主から提供された資金を元に事業活動を展開し、利益を追求します。この利益の一部は、配当として株主に還元されることが期待される。このような経済的な関係性の中で、株主と会社、特に経営者との関係は深化していきます。
株主と経営者の関係
株主は会社のオーナーとしての立場にあり、経営者や取締役との関係性が形成されます。この関係性は、単に資金提供者と受け手というだけでなく、経営方針や事業戦略に関する意見交換や議論の場としても機能します。
特に、大株主や機関投資家の場合、経営者とのコミュニケーションが頻繁に行われ、経営の方向性や戦略に影響を与えることが一般的です。経営者は、株主の期待や要望を理解し、それを経営に反映させることで、企業価値の向上を目指します。
株主の影響力
株の保有割合や持ち株の種類によって、株主が会社の経営に与える影響は異なります。大株主や特定の権利を持つ株主は、株主総会での議決権を行使することで、経営方針の決定や経営者の選任など、重要な決定に影響を与えることができます。
また、持ち株の種類によっては、特定の事項に対する優先的な権利や、経営に関する情報へのアクセス権を持つこともあります。このように、株主の影響力は、その持ち株の内容や状況によって大きく変わることが特徴的です。
株主の主な権利
株主になると、様々な権利を得ることができます。ここでは、株主になることで得ることができる主な権利についてご紹介します。
配当権
配当権とは、株主が会社の利益を分配として受け取る権利を指します。会社が一定の期間(通常は1年)の経営活動を通じて利益を上げた場合、その利益の一部が株主に分配されることが一般的です。
この分配される利益のことを「配当」と呼びます。配当の額や頻度は、会社の経営状況や方針、業界の慣行などによって異なります。また、配当は現金の形で支払われることが多いですが、株式や他の資産の形で分配されることもあります。配当の支払いは、株主総会での承認を経て行われることが一般的です。
議決権
議決権とは、株主が会社の重要な決定に関与する権利を指します。株主総会は、会社の最高意思決定機関として、経営方針や重要な事項についての決定を行います。株主は、保有する株式の数に応じて、この総会での投票権を持ちます。
この投票権を行使することで、経営者の選任や経営方針の承認、重要な事業の承認など、会社の方針や活動に影響を与えることができます。
残余財産分配請求権
残余財産分配請求権とは、会社が清算される際に、その残余財産を株主に分配する権利を指します。具体的には、会社が倒産や解散などの理由で清算される場合、その資産から債務を支払った後の残りの財産(残余財産)が存在する場合、その財産は株主に分配されます。
この際の分配額は、株主が保有する株式の数に応じて決まります。この権利は、会社が経営破綻するリスクを背負う株主に対する、最後の保護措置とも言えるものです。
株主優待
株主優待とは、会社がその株主に対して、商品やサービスの割引、特典提供などの形で行う優遇措置を指します。株主優待は、株主を増やすためや、長期的な株主を獲得・維持するための手段として多くの企業が実施しています。
優待の内容は、会社の業種やサービス、商品に応じて様々で、食品や雑貨の割引、イベントへの招待、限定商品の提供などがあります。株主優待は、配当とは異なり、必ずしも利益に直結しない形での還元となります。
企業が株主を増やすメリット
企業が株主を増やすことは、その経営や成長戦略において多くの利点をもたらします。新たな資金の流入や市場での認知度の向上は、企業の競争力を高める要因となり得ます。また、多様な株主からの意見やフィードバックは、企業の経営をより健全で効果的なものにする手助けとなるでしょう。以下では、株主を増やすことによる主なメリットについてご紹介します。
資金調達の容易化
企業が株主を増やすことで、新たな資金を調達することが容易になります。特に、大規模な投資や事業拡大を計画している場合、外部からの資金調達は非常に重要です。
株式の公募や増資によって、新たな株主から資金を受け入れることができ、これにより企業は成長を加速させることが可能となります。また、資金調達の手段として株式を利用することで、高利の借入に頼ることなく、比較的低コストでの資金確保が期待できます。
企業の知名度やブランド力の向上
新たな株主を増やすことで、企業の知名度やブランド力が向上する可能性があります。多くの人々がその企業の株主となることで、その企業に関する情報やニュースが広く伝播しやすくなります。これにより、企業の商品やサービスへの関心が高まり、結果的に売上や利益の向上に寄与することが期待できます。
経営の安定化
多くの株主を持つことで、経営の安定化が図られる可能性があります。一部の大株主の意向に左右されるリスクが低減し、経営の独立性や自主性が保たれやすくなります。また、多様な株主からの意見やフィードバックを受け取ることで、経営の方針や戦略のブラッシュアップが期待できます。
企業が株主を増やすデメリット
一方、企業が株主を増やすことは、必ずしもポジティブな結果だけをもたらすわけではありません。増加する株主とのコミュニケーションや、市場での株価の変動は、経営に新たな課題を投げかけることとなるでしょう。また、経営の透明性やコーポレートガバナンスの要求も強まり、企業の運営において柔軟性を失うリスクも考慮しなければなりません。
経営の透明性の要求
株主を増やすことで、経営の透明性が求められるようになります。多くの株主からの監視の目が向けられるため、企業の経営情報の開示やコーポレートガバナンスの強化が必要となります。これにより、企業の経営において柔軟性が失われるリスクがあります。
株主とのコミュニケーションコストの増加
多くの株主を持つことで、株主とのコミュニケーションコストが増加します。株主総会の開催や、株主への情報提供、質問への回答など、株主との関係を維持・深化させるための労力やコストが増大します。
株価の変動リスクの増加
多くの株主が市場で株式の売買を行うことで、株価の変動が激しくなる可能性があります。特に、短期的な利益を追求する投資家が増えると、株価の乱高下が起こりやすくなり、企業の経営や資金調達に影響を及ぼすリスクが高まります。
企業が株主からの評価を高める方法
企業の成功は、その製品やサービスの質だけでなく、株主や投資家からの信頼と評価にも大きく依存しています。高い評価を受けることで、資金調達が容易になり、企業の成長や拡大が加速される可能性が高まります。
以下では、企業が株主からの評価を高めるための具体的な方法について詳しく探っていきます。
透明な経営情報の開示
企業が株主からの評価を高めるための最も基本的な方法の一つは、透明な経営情報の開示です。企業の財務状況、業績予測、経営方針などの情報を定期的に、そして正確に公開することで、株主は企業の現状や将来のビジョンを理解しやすくなります。
また、外部の専門家や監査法人による監査を受けることで、情報の信頼性を高めることができます。透明性の高い情報開示は、株主との信頼関係を築く上で不可欠です。
持続的な配当政策
株主は投資のリターンとして配当を期待しています。そのため、安定的かつ持続的な配当政策を採用することで、株主からの評価を高めることができます。具体的には、一定の配当性向を維持する、または業績が好調の際には増配を行うなどの方針を明確にし、株主に対する還元の姿勢を示すことが重要です。
コーポレートガバナンスの強化
近年、コーポレートガバナンスの重要性が高まっています。経営の透明性を高め、経営者の責任を明確にすることで、企業の持続的な成長を支える体制を築くことが求められています。外部取締役の導入や、経営監督機能の強化など、具体的な取り組みを進めることで、株主からの評価を向上させることができます。
積極的な株主コミュニケーション
株主とのコミュニケーションを積極的に行うことも、評価を高めるための重要な手段です。定期的な株主総会の開催はもちろん、業績説明会や株主向けのセミナーを開催することで、株主との直接的なコミュニケーションの機会を増やすことができます。
社会的責任の履行
企業が社会的責任を果たすことは、株主だけでなく、多くのステークホルダーからの評価を高めるためのキーとなります。環境保護活動や地域社会への貢献、従業員の福利厚生の充実など、企業としての社会的責任を積極的に履行することで、株主からの信頼を獲得することができます。
株主とのコミュニケーションなら
リンクコーポレイトコミュニケーションズ

リンクコーポレイトコミュニケーションズでは、株主と企業との積極的な対話を支援しています。
サービスとしては、長期的な視点で応援し、企業と株主がともに成長する株主コミュニケーション支援をする、「株主通信」の制作や、会社の最高意思決定機関であり、株主との対話の機会である「株主総会」の配信支援を提供しています
さらに、個人投資家と上場企業を繋ぐコミュニケーションツール「e-株主リサーチ」では、個人投資家との対話を通じて、投資家の情報ニーズを可視化する、個人株主・投資主向けのオンラインアンケートサービスを提供しています。
まとめ
「株主」とは、株式を保有することで会社の一部の所有者となる人々のことを指します。株主は、投資としてのリターンや、会社の経営に関与する権利を持つなど、株式市場において重要な役割を果たします。株主の基本的な概念や権利を理解することは、賢明な資本市場へのアプローチをするための判断を下すための第一歩となります。
株主についてよくある質問
「株主」とは具体的にどのような存在ですか?
「株主」とは、ある企業の株式を保有する者を指します。株式を購入することで、その企業の一部の所有者となり、企業の利益や成長に応じたリターンを期待することができます。
具体的には、企業が利益を上げた場合、その利益の一部が配当として株主に分配されることが一般的です。また、株主は保有する株式の数に応じて、企業の経営方針や事業計画に関する意思決定に参加する権利も持っています。
株主の主な権利は何ですか?
株主の主な権利には、配当を受け取る権利、株主総会での議決権、企業の財務情報や経営方針に関する情報を知る権利などがあります。
特に、株主総会では、経営者の選任や重要な事業計画の承認など、企業の将来に関わる重要な決定が行われるため、株主としての議決権は非常に重要です。
株主と取締役や経営者との関係はどのようなものですか?
株主は企業のオーナーとしての立場にあり、取締役や経営者は株主から選任され、企業の経営や事業活動を行う責任を持っています。経営者は、株主の利益を最大化するための経営方針や戦略を立案・実行する役割を担います。
一方、株主は、経営者の活動や業績を監視し、必要に応じて経営方針の変更や経営者の交代を求めることができます。